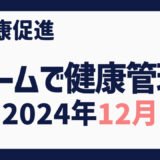円熟期を迎えた作り手による大作、名作、ドリームプロジェクトが目白押しのスーパーファミコンタイトル。
ファミコンで大きく花開いた家庭用ゲームが、スーファミである種の “極み” に達した時代でした。
図表
読解
スーパーファミコン 国内トップ10
> 序盤
スーパーファミコンの立ち上がりは意外に静かです。
国内だけとはいえ、1年目のミリオンセラーが「スーパーマリオワールド」(1990年11月)と「ファイナルファンタジー IV」(1991年7月)の2タイトルだけというのは少し驚き。
ちなみに、ファミコンの日本国内 “ミリオンセラーソフト” が39タイトルだったのに対し、スーファミは29タイトル。
まあ1992年くらいまでなら、ファミコンもまだまだ “現行機” レベルで遊ばれてましたからね。
> 中盤
そんな中、当時、全国各地のゲーセンで “空前絶後” とも言えるくらいの格ゲーブームを巻き起こした「ストリートファイター II」(1992年6月)がスーファミに移植され、「ファイナルファンタジー IV」(1991年7月)や「ドラゴンクエスト V」(1992年9月)を超える290万本のセールスを記録。
「マリオ」、「ドラクエ」、「FF」と並び、「ストII」もスーファミ中期(おそらく黄金期)を支える代表作となります。
そして、いつの時代もとにかく売れ続ける「マリカ」の始祖、「スーパーマリオカート」(1992年8月)がスーファミで誕生。
> 終盤
そして、1995年以降は、もう “スーファミ後期~末期” と言っていいかもしれません。
この頃は、1994年11月にセガから「セガサターン」、そして翌月12月にソニーから「初代プレステ」と、いわゆる「32ビット機(当時の “次世代機”)」が次々と市場に投入され、16ビット機のスーファミに「時代遅れ」感が出てきたのは否めません。
しかし、それでもファミコン登場から11年以上、そしてスーファミ登場からも4年以上経過し、作り手側も円熟期を迎えていたのでしょう。
スーファミ後期も名作ぞろいです。
まずは、ファミコン初期以降あまり名前を聞かなかったものの、”超美麗グラフィック” で華麗に復活を果たしたのが「スーパードンキーコング」(1994年11月)。
また、坂口博信・堀井雄二・鳥山明によるドリームプロジェクト「クロノ・トリガー」(1995年3月)の「ゴージャス感」は、後にも先にもちょっと類を見ないレベル。
そして、前作から3年以上経過し、当時としては待ちに待たされた大作「ドラゴンクエスト VI」(1995年12月)に、任天堂とスクウェアのまさかの共同開発による、RPGのコマンドバトルにアクション要素も取り入れた「スーパーマリオRPG」(1996年3月)などなど。
いずれも横スクロールアクションやRPGという、当時としても使い古されたゲームシステムだったと思います。
しかし、なんかこう・・・今から見ても “華” がありますよね。
当時の2Dドット絵も、複雑なモザイク画のようであり、しかしブラウン管テレビに映し出されたその絵は、写実的な名画を思わせる陰影に富んでいて、何とも言いがたい独特の美しさがありました。
ファミコンで大きく花開いた家庭用ゲームが、スーファミである種の “極み” に達した時代だった気がします。
補完
注記
図表タイプ
バーチャートレース(Bar Chart Race、BCR)
対象期間
1990年11月から1998年7月まで
情報源
◆任天堂タイトル:決算資料(IRライブラリー)、主要タイトル販売実績
◆スクエニタイトル:決算資料(IRライブラリー)
◆カプコンタイトル:決算資料(IR資料室)、ミリオンセールスタイトル
◆その他タイトル:2021 CESAゲーム白書、2023 CESAゲーム白書
(なお、「CESAゲーム白書」は完全リニューアルされ、2024年度から「CESAゲーム産業レポート」として刊行)
略称表記
各ゲームタイトルのバーをタップするか、マウスホバーしていただくと、そのゲームの正式名称・対象コーンソール・発売日が表示されます(ツールチップ機能)。
その他
あくまで当ブログが、一般に公開されている情報を集めて「出荷本数データ」として集計しているにすぎません。日本国内で販売され、流通したすべてのゲームタイトルを網羅しているわけではない点につき、ご了承ください。
各タイトルごとの月間の売上本数も、そのすべてを第三者が正確に把握することは不可能なので、当ブログが考える「ゲームソフトの売れ行きに関する一定の基準」で調整しているデータが含まれます。
なので、もし上記の「情報源」以外に一般的に閲覧できる良い時系列データがあれば、ぜひコメントなどで教えてほしいです。
以上
 ガッツの夜明け
ガッツの夜明け