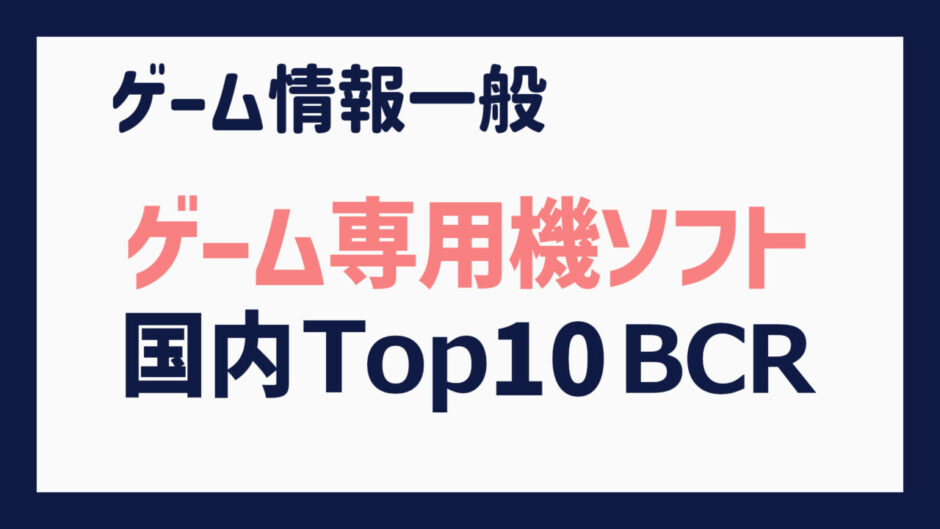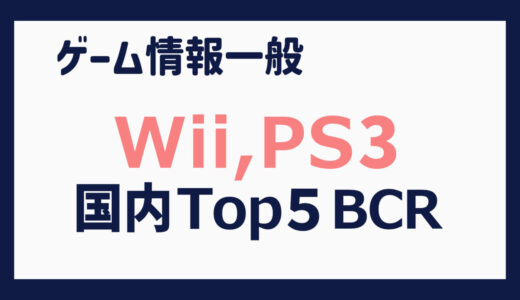ファミコンからNintendo Switchまで国内ゲームの波乱万丈な歴史を、1983年7月から2024年3月までの約41年分のゲームソフト出荷本数データをベースに一気通貫で体感できるBCRです。
図表
【ゲーム専用機】国内上位10タイトルの出荷本数推移(バーチャートレース形式、5分42秒)
読解
国内ゲームソフトのバーチャートレース総集編ということで、1983年7月から2024年3月までの国内ゲームソフト出荷本数データを使った約41年分の一気通貫BCRです。
6分近くのアニメーションになったため、今回は特に編集もしていませんし、音楽も付けていません。
私もそうですが、ファミコン世代の方であれば、この動画の最初から最後まで、自分のゲーム体験やその時々に経験した出来ごとと照らし合わせて楽しめるのではないでしょうか。
一方、もし「古すぎる時代のことはわからん」という方は、下記の「機種別バーチャートレース一覧」から各機種・世代のゲームの売れ行きを振り返ってもらえれば、ある程度楽しめると思います。
ファミコンからNintendo Switchまで、国内ゲームは波乱万丈の歩みでした。
機種別バーチャートレース一覧
ファミコン
ファミコンといったら「マリオとドラクエと野球ゲーム」。
小学生が友だちの家に集まってファミコンで盛り上がり、そこの家のお母さんに「いいかげん外で遊んで来い」とキレられる、なんて日常がただただ懐かしい。
ゲームボーイ
据置機のスペック競争なんかお構いなしに1億1800万台売れたゲームボーイ。
日本国内での “ミリオンセラーソフト” は意外に少ないですが、1996年にあの “バケモノ” コンテンツを生み出しました。
スーパーファミコン
円熟期を迎えた作り手による大作、名作、ドリームプロジェクトが目白押しのスーパーファミコンタイトル。
ファミコンで大きく花開いた家庭用ゲームが、スーファミである種の “極み” に達した時代でした。
セガサターン/プレイステーション/NINTENDO N64
いわゆる「32ビット機」の登場による本格的な3Dゲーム時代の幕開けと同時に、ソニー参入に伴うゲーム業界の地殻変動とその裏で進むゲーム離れ現象など、国内ゲームの1つの転換点ともなった混沌の世紀末。
プレイステーション2/ゲームボーイアドバンス/ニンテンドーゲームキューブ
据置機でも携帯機でも、なんとなくゲームに行き詰まり感や尻すぼみ感が漂う2000年代。
人気シリーズであっても続編が1作目を越えられないタイトルが多く、ゲーム業界が一番沈んでいた時期かもしれません。
ニンテンドーDS/プレイステーションポータブル
DSが「グラフィックの豪華さや、より高度で複雑に凝ったゲームシステム」とはほど遠いタイトルで次々とミリオン越えを連発。
ゲーマーと非ゲーマーの壁をぶっ壊したという意味で、まさしくイノベーションでした。
Wii/プレイステーション3
WiiがDSに続いて巻き起こした “レボリューション” を振り返るとともに、「なんかWiiって最初はスゴイ話題になったのに、いつの間にか話を聞かなくなったなあ」みたいなモヤモヤの正体も探ります。
ニンテンドー3DS/Wii U
非ゲーマー層の新規開拓に成功したDSとWiiに続き、さらなる「ゲーム人口の増大」に向けて投入された後継機のニンテンドー3DSとWii U。
しかし、その道のりには大きな困難が待ちかまえていました。
Nintendo Switch
2000年代初頭に「ゲーム人口増大」という目標をかかげてまかれた変革の種は、DSとWiiで芽吹き、3DSとWii Uでの厳しい環境に負けることなく成長を続け、ついに見事な大輪の花を咲かせました。
補完情報
注記
グラフ形式
バーチャートレース(Bar Chart Race、BCR)
期間
1983年7月~2024年3月
情報源
◆任天堂タイトル:決算資料(IRライブラリー)、主要タイトル販売実績
◆スクエニタイトル:決算資料(IRライブラリー)
◆カプコンタイトル:決算資料(IR資料室)、ミリオンセールスタイトル
◆その他タイトル:2021 CESAゲーム白書、2023 CESAゲーム白書
(なお、「CESAゲーム白書」は完全リニューアルされ、2024年度から「CESAゲーム産業レポート」として刊行)
タイトル略称
「機種別バーチャートレース一覧」から各記事のリンク先に飛んでいただき、「補完情報」を参照ください。
その他
あくまで当ブログが、一般に公開されている情報を集めて「出荷本数データ」として集計しているにすぎません。
日本国内で販売され、流通したすべてのゲームタイトルを網羅しているわけではない点につき、ご了承ください。
なので、もし上記の「情報源」以外に一般的に閲覧できる良い時系列データがあれば、ぜひコメントなどで教えてほしいです。
また、各タイトルごとの月間の売上本数も、そのすべてを第三者が正確に把握することは不可能なので、当ブログが考える「ゲームソフトの売れ行きに関する一定の基準」で調整しているデータが多数含まれます。
あくまで「売上レースっぽい雰囲気を楽しむもの」とご理解いただければと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
 ガッツの夜明け
ガッツの夜明け